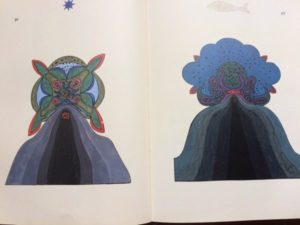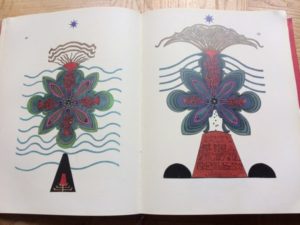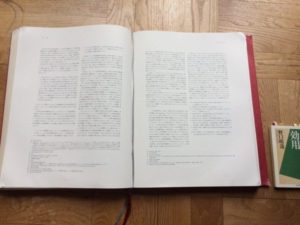現在、指導室にはカウンセリング用のソファーが置いてあるのだが、実はこの「椅子」は直近の3年余りで何回も出したり引っ込めたりしている。
日本人の身体文化、というか坐り方が現代的に全く統一されてないためにやむなくこんなことを繰り返してきたと言える。
椅子を置かないときは絨毯に正坐していただくのだが、そうなると正坐が出来ない人にとっては身心が非常に異質な感覚に包まれて対話どころではなくなってしまうのである。
ところがそういう人がソファに坐るとたちまち饒舌になるところが興味深い。下半身の体勢と口唇運動がこうも密接につながっているものかと、こちらは探求心を煽られる。
ともかくカウンセリングというのは話してもらうことがそのまま自己分析と治療みたいなものなので、これはこれでなかなか重宝するのだ。
一方でソファに坐るのを嫌がる方も一定いらっしゃる。全般に40歳以上の方に多いけれども、この様な方は腰が無格好に沈むソファーの方がかえって落ち着かないのである。
実は椅子座というのは意識活動が亢進して、身体感覚が希薄になりやすい。だから上述の人たちからすれば、整体指導を受ける身心の「構え」というのが事前に形成されにくいのである。
この、両極のはざまでどちらを取るか呻吟した結果として、最初に述べたようなソファ⇔正坐の行ったり来たり現象を生んだ。
従来なら野口整体と言えば和服に正坐、平伏だが、そうも言ってられないのが平成日本の現状なのだ。
そもそも野口先生がもっとも活躍された時代は昭和30~40年代である。この時代の日本人の身体にはまだまだ正坐の文化が活きており、また正坐は対話のための一つの礼式・型であった。
だから特定の場や人に対して改めて礼を示すときには当然正坐の構えを取るし、整体操法がきちっと決まり身体の中心軸と重心位置が臍下丹田にぴたっと決まれば身体はなお一層この型の中へ落着する。
いうなれば整体操法とは、その人が生まれてから培ってきた「身体の規定位置」までその身心を戻してやることが仕事の実態なのだ。
ところが現代はその身心の規定位置の具現体であった「正坐」の身についていない人が日々増え続けているのである。
かつてはもともと備えた規定位置に帰してやればよかったものが、現代的には身心の帰るべき「家」を新たに構築してやらなければならないのである。
つまり30歳を過ぎ不惑に手が届きそうな方々を相手に、人生初の身体教育を施すことが整体指導の実状となっているのだ。
だから往時に比べれば現代の整体指導はそれだけ歳月も要するし、苦労も多い。
しかし考えてみれば身体とは心を納むる大切な器なのである。
よってこの器の形成(体育)なくして精神の恒常的な安定を図ることなど到底不可能なのである。現代日本におけるうつ病や自律神経失調症の罹患率の多さはこの恐るべき事実を雄弁に物語っているのだ。
ちなみに「昔はよかった」というのは文化の変遷についていけない古老たちの嘆きだが、過去の文化やそれに直結した身体性がいかに素晴らしかったとしても人類史上、文化が逆行したためしはないのである。
「今をよく生きる」ということは現代文明と現代の身体性をフルに活用し、また新たな型を創造していく過程の中にある。
よって整体指導の中で何をやるべきか、ということを常に考えつづ進化させることは指導者の宿命とも言えるだろう。
現代日本社会の中で正坐を再興し浸透させようと頑張ることはナンセンスかもしれないが、一方でこれを求むる人に伝うるべく自ら修め、範を示すことにもなお意義を感じる。
ここで虎の威を借りるようだが、仏道の坐禅という行法があらゆる文化の変遷を超越して今日までその命脈を保ってきたという事実に倣いたい。
そしてこれからも日本人の身体と文化の潮流を見つめ続けることに、強い関心とある種の義務感を感じている。