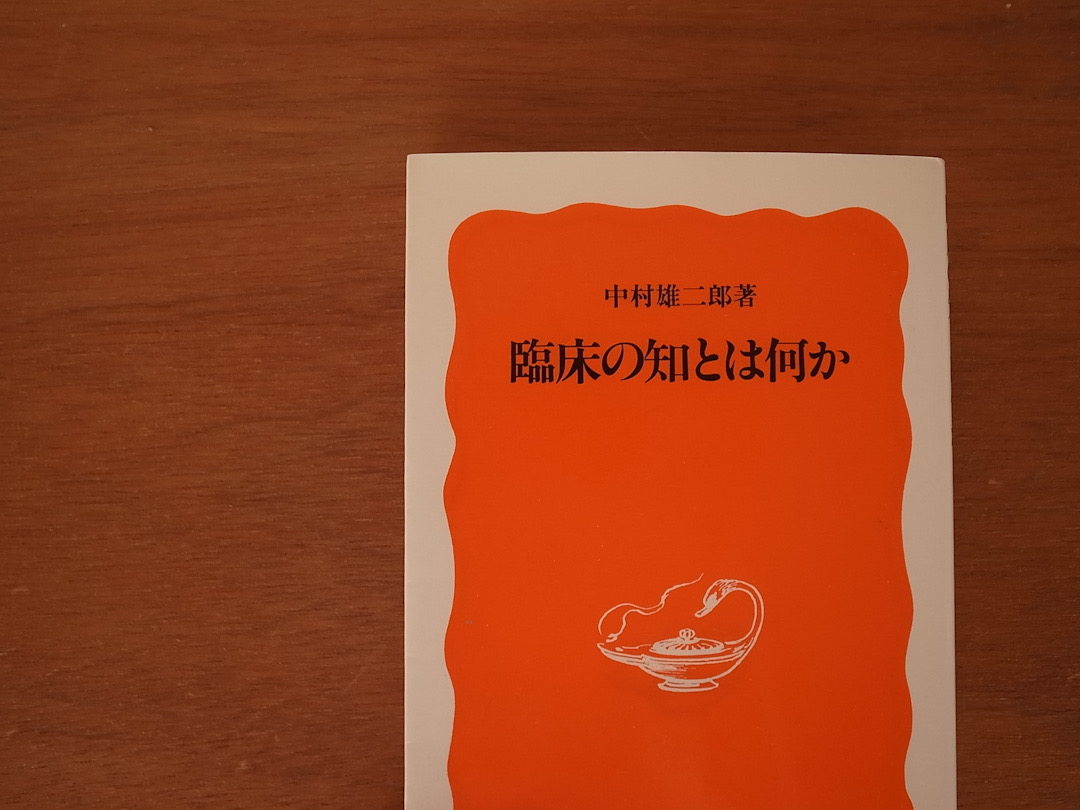鈴木哲也・高瀬桃子 著『学術書を書く』を読んだ。学術書を書いて出版するまでの道のりを懇切丁寧に纏めてある一冊。
現代はインターネットの普及によって情報の発信や受け取り、また公開された内容の修正や改変のスピードは格段に上がった。
このような状況下にあって出版から販売に至るまで多くの時間と労力を要する書物を出すことに果たして意義があるのだろうか、という考察が本書の冒頭でなされている。
本稿の見出しの「知識か「情報」か」、というのは本書につかわれた見出しの一つである。知識、情報、この二つの差異はいかなるものなのだろうか。
筆者によれば知識といった場合、そこには個人に染み付いた身体性を伴う知恵としての働きが含まれるという。
確かに知識を身に着けるという表現はあっても、情報は身に着けるとは言わない。
情報という言葉は必要に応じて拾ったり、人に渡したりできる手軽さを感じさる。つまりは情報とは人間と遊離した概念といえそうである。
現代は「情報の氾濫」などという言葉が定着して久しいけれども、確かに携帯電話などデバイスの発達のおかげで情報はどこにいてもいくらでも手に入る。
生活上の利便性という点では優れているが、それがそのまま心の安定につながるかというとそうとも言えないだろう。
「情報に振り回される」という表現もあるくらい、情報があってもそれを判断し取捨選択するちからがシッカリしていないと、かえって余分な不安や焦燥に駆られたり、イライラしたりせねばならない。
そういう点で、情報に自在にアクセスできるという状態と、知識が身についている、ということは大きく違うように思われる。
情報の取得に比して、知識を身に着けるには相応の時間や労力を要するのだ。
昔の大学生は自分の専門外の本でも一般教養として何日もかけて読んだそうだが、現代の学生は一か月に一時間も本を読まない人がいるという。
私自身どうだったか考えると、一か月の総読書時間が5時間を割っている月もざらにあったかもしれない…。当然一般教養は身についていない。
加えて、今やレポートや論文の提出もネットで拾った情報のつぎはぎで通ってしまいかねない世の中である。
こうなると一冊の本を辞書を引き引き読み進め、ガリゴリと咀嚼して知識を身に着ける力など到底養われないだろう。
その結果、本と言えば流動食みたいな軽いハウツー本や名言集しか手に取らず、ネット上で出所不明な情報ばかりを読みあさる人は増えていく。これでは情報を管理する母体としての強固な知識が養われる見込みはない。
これは非常に危うい状態である。
そういう考察から、結論として学術書を出版することはもちろん、読むことにも大いに意義があるのだ。
途中から本の内容か自分の主張か混ざり合って分からなくなってしまったけれども、現状のコロナがどうこう…といっている世相にあって一点思うところがある。
ネットで取得する情報には大きな陥穽があるのだ。
それは何かというと、ネットで情報収集した場合は自分にとって好ましい情報や都合の良い内容に偏りやすいのである。
例えばワクチンの成否、功罪という点を例に挙げると、肯定派の人は最初から肯定的な情報を目掛けて集め読む傾向に走りやすい。そして検索エンジンの性質上このようなことが可能なのである。途中で否定的な見解を見つけても、「これはおかしい(気に入らない)」と目をつぶって消してしまえばそれで済んでしまう。
当然だが否定派の人もまた同じで、はじめから否定的な見解を呈する発信者やコミュニティのサイトをよりどって元々の自分の見解を強化するための材料確保に走りやすい。
このような態度では自分の見解に発展的な広がりが生じる余地はない。選り好みした情報の取捨選択はもはや「学び」とは呼べないだろう。
ネットが普及する以前の、つまり本の時代だったらこのような問題は生じにくい。
紙の出版となると雑誌を一冊出すのでも「確かな人」でなければ寄稿はできない。発刊される際には、どこの誰が、いつ書いたものか、くらいは最低限明かになる。
単行本の出版となるとさらに厳しい審査の目をくぐらなければならない。学術書ともなれば出版の前に繰り返し査読が行われるし、出版された後には同業の専門家たちによる点検と批評を受けることになる。
このような経緯を経てなお増刷再版されて生き残っていくためには、一つの主張を述べるにも、いちいちその論拠を明らかにし着実に歩を進めなければならないのである。
先のワクチンの是非について考えるなら、スマホを手放して図書館に行って調べるとなるとワクチンに関する様々な本の背表紙に出会うことになる。
気になるタイトルのものを手に取って、目次を見ると自分が予測していたものを大きく飛び越えた見出しがいくつも出てくるだろう。
そこから興味の湧いた本を数冊読むことで、自分が要求していた情報の二回り三回り外周のものまでが獲得されることになる。
これによりワクチンは是か非かとしか頭になかった人でも、否定と肯定を包括する大きな知識に触れることができる。
いわゆる弁証法の正・反・合というプロセスもここから生じる。
つまり一旦は自分の考えを否定する見解に触れ、抵抗しながらも咀嚼し、消化、そして受容を経ることをもって私は「学び」と考えたいのである。
そのためには本の存在は不可欠であるし、むしろ今こそ本が見直されるべきだとも思う。
言っておきながら私はそこまで本を読んでもいないのだけれど、『学術書を書く』を読むと一冊の学術書が出るまでのさまざまな工程に触れて、これまで読んできた本のありがたみが増した次第である。
ちなみに続編の『学術書を読む』には、学術書を読むにあたって何を読んだらよいのかという本の選定の方法、そして読み方についても詳述されている。
忙しくて本など読む暇がないという人も多いかもしれないが、端末を開く時間をちょこちょこ集めてれば一日一時間、30分くらいは読書にまわせるのではないだろうか。
かく言うこの記事がブログであるというのが皮肉なのだが…、時にはスマホを置いて、本の世界に出かけてみるのもいいのではないだろうか。