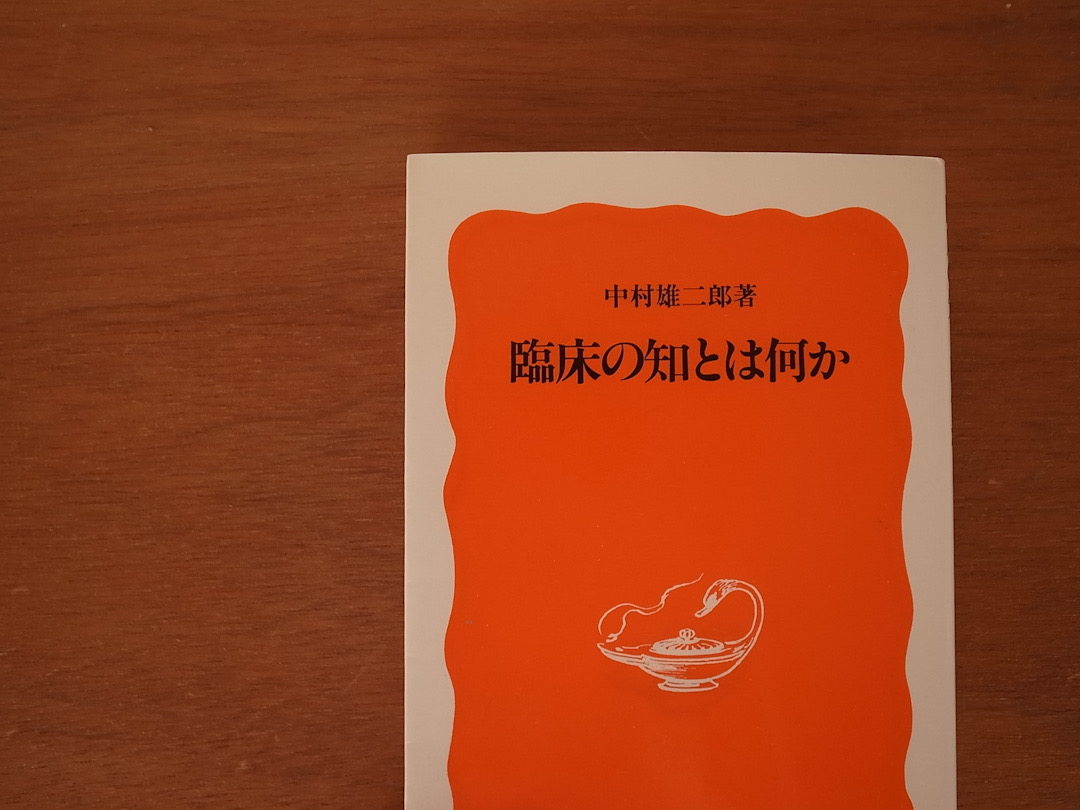何年か前に買ったっきり積読(つんどく)してあった中村雄二郎著『臨床の知とは何か』(岩波新書)をようやく読んだ。
新書というライトなボリューム感から油断したが、かなり歯ごたえのある本気度の高い学術書である。
内容は近代科学(科学の知)と臨床の知の対比が主要テーマになっている。
野口整体を実践する立場からすると、西洋医療と整体法の対比構造がほぼそのまま当てはまるので本著の内容は多くの重要な示唆に富んでいた。
科学の知とは簡単に説明すると、次のようになる。近代科学における現実認識は<普遍性><論理性><客観性>という3原則を具えていることが求められる。これらを踏まえて得られた現実認識が科学の知である。
ここで<科学の知>を理解するために思い切った具体例を挙げるなら、次のようになる。
「カレーという食べ物を理解する」ために材料をはじめ物質的なデータから導き出して、その実体を追求していくのが<普遍性><論理性><客観性>の三つを兼ね備えた科学的な理解である。
対して「臨床の知」とは、言うまでもなく「食べる」ということに尽きる。食べると味覚という点で大変な情報量が瞬時に展開する。これが文字通り臨床の醍醐味である。
科学的な方法でカレーの分析・研究を100年やってもカレーの味は絶対にしない。百聞は一見に如かずという諺もあるように、文字や数値を使ってどんなにデータ化しても「食べる」という行為で得られる感覚には及ばないのである。
こう書くと科学の知がいかにも無意味で愚かしく見えるけれども、実際はそうとも言い切れない。
たしかにカレーを食べたら「おいしい」とか「辛い」とかは即座にわかるし、毎回材料を加減しつつ入れ替えをしていけばその都度味の検証とおいしさの追求もできる。
しかしその「味」という感覚は個人の主観に拠っている。まずお腹がすいていれば何を食べてもそこそこはおいしいだろうし、満腹なら同じものを食べてもうまくない。あるいは「激辛」という表現も個人の辛味に対する耐性度合によって異なるために客観性に乏しい。
そのため、得られた感覚を情報化して万人に説明するために、客観性をそなえた解説がなされることは十分役に立つのである。
例えば、カレー粉のグラム数や配合率、具材(人参何グラムを何々切りにする)を文字や数値にすることで、データ化してお互いに授受できる。これが客観性の便利さである。
では科学をベースにした近代文明の何が問題かというと、物事を理解しようとするうえで<普遍性><論理性><客観性>に「偏り過ぎた」場合である。
先の例から極端な言い方をすると、カレーを一度も食べたことのない人が文字でカレーの勉強をしてカレー屋をやる、というようなことが起こってくる。
「そんな馬鹿な事あるか」といわれるかもしれない。ところがこれを現代医療の例に差し替えると、腰痛に一度もなったことのない医師が椎間板ヘルニアの手術をする、ということになる。これなら現代社会で十分行われていることであろう。
また教育現場なら、お米を一度も作ったことのない先生がお米の作り方を生徒に読んで教える。アメリカに行ったことのない先生が、アメリカとオーストラリアと日本の国土の違いを説明する。
こういうことが当たり前、としてまかり通っているのが科学をベースにした文明国の実態である。
一つ一つ挙げていくとあまり大きな問題に発展しないことが多いけれども、このような態度は時に近代科学文明の大きな陥穽となって私たちを予想外の結果に導くことがあるのだ。
例えば「新薬」と呼ばれるものの中には、使ってみて初めて分かる副作用がある。比較的記憶に新しいものとしてはタミフルと異常行動(飛び降り・転落)の関連性などが思い出される。
この件については関連を証拠付ける要素が検出されず(そもそも適切な検証がなされたのか不明であるが)現在もうやむやのままである。
科学的な研究というのは一見して公平性を匂わせているものの、実際は研究に携わる人の社会的な立場や研究にかけられる費用、また結果に求められる緊急性やニーズの規模などが複雑に絡み合って、得られた結果を見る目にバイアスがかかりやすいのである。
先の例でいえば、タミフルの異常行動で事故死した人が少ない場合、その研究に興味を抱く人も少なくなる。そうなると当然ながら研究で得られた結果に対して費用面の見返りもさほど見込めない。
さらには、そのような重要な副作用があることを後から認めてしまった場合、十分な検証をせずに流布した当局の責任が問われかねないのである。そのため検証に対してはどうしても消極的にならざるを得ない、といったことが考えられる。
このような科学文明の陥穽を鋭く見つめ補うものとして、前掲書では<臨床の知>という立場に可能性が見出し着目しているのだ。
カレーを作るなら、過去のデータに頼って作るのではなく、味見をしながら「うまいか、まずいか」ということから出発して、その内容を参究していこう、というのが臨床の立場である。
新薬の効果でいえば、あらかじめ建てられた仮説や学説からまったく独立したまっさらな目で臨床の結果を見つめ、受け入れることである。
となれば、いきおい近代科学と<臨床の知>は対立が起こりやすい。しかしながら、科学文明の見えざる弊と限界を乗り越えるためには、それぞれの立場を越えた協力関係が求められるのである。
これについて『臨床の知とは何か』の筆者、中村雄二郎は次のように提言する。
…<臨床の知>の主導下に科学的医学の諸成果を思い切って取捨選択し、再組織することであろう。医学・医療において高度化した科学や技術の自己目的化や自己満足は、<臨床の知>によって初めてチェックすることができるからである。また、それがそのまま、医療を、商業主義と結びついた科学や技術による奴隷状態から、人間の手に、生活世界に取り戻すことになるのである。
と、以上の箇所に簡潔に纏められているのだ。
この本が出版されたのは1992年のことなので、かれこれ30年近く前になる。
にもかかわらず依然として科学文明の陥穽はいたる所に存在し、我々を真実から遠ざけていることは少なくない。
このような構図をよく吟味したうえで、私たちは科学文明の落とし穴に慎重にならねばならないのである。
客観から出発した科学はその理論の実践から得られた結果に謙虚である必要があるし、臨床から得た体験知はその確かさをより堅固なものとするために<普遍性><論理性><客観性>の目に堂々と晒される必要がある。
言うまでもな整体法は後者に寄っている。そのため野口整体は創始者の真意がよく伝わらず、代替療法という分野に括られ何かと疑わしい目で見られることも少なくない。
他でもない<客観性>の乏しさがその主な原因と言えよう。
整体に関わる者としては、近代科学と<臨床の知>の対比構造を理解した上で、<論理性>を見出しながら公共性を付与していくことが今後の重要な課題ではないかと考えている。