健康な人の自我は、身体と同一視されており、病的な人の自我は、体との確固たる同一視を持っていない。アレキサンダー・ローウェン著 『引き裂かれた心と体』 創元社
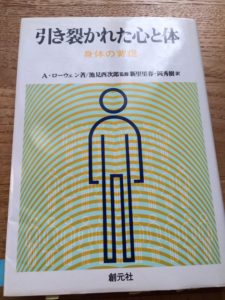 上記は少し堅めの学術的な文章の引用だが、いわゆる「うつ」や「がん」のような現代的な病の原因を、肉体から引き離された自我(理性)にあることを看破している。
上記は少し堅めの学術的な文章の引用だが、いわゆる「うつ」や「がん」のような現代的な病の原因を、肉体から引き離された自我(理性)にあることを看破している。
ここでの「肉体」とは「感情を有する生きた身体」のことで、この肉体から意識が離れることは生活から感情体験が薄れていくことを意味しているのだ。
生命活動の根源はやはり感情エネルギーであるといって相違ないもので、感情が希薄になることは生活からだんだんと温度や勢いがなくなっていき身体も固く冷たくなっていきやすい(凝りや冷えの慢性化)。
整体指導の場ではもっぱら身心の深いリラックスを促して、「感情の気づき」を介助することが主眼である。著作の中ではヨガから着想を得たバイオエナジェティックス・セラピー(生体エネルギー療法)という一種の体操(?)が紹介されている。一方野口整体では、この感情の解放を助ける方法に相当するのが活元運動(自働運動・霊動法)にあたるだろう。
ごく個人的感想として、過去4,5年の読書遍歴の中ではこのA・ローウェンの著作は秀逸である。これほど身体疾患と感情抑圧とのつながりを臨床例と供に学術的に述べた本を知らない(知らないだけで他にもきっとあると思いますが)。
洋の東西などという区分はあくまで思想的概念でしかなく、「人間」というのはある面では万国共通なものである。したがってその人間を探求していくとやはり答えも一つに集約されるのだろう。
こうして見ると病むことも治ることも、本来は難しいことは一つもない。頭を休めて、身体の自然の動きの任せる、というそれだけでいいのだから。
ただ「工夫」に慣れ親しみ過ぎた人は、この何もしないで任せる、ということがやっぱり難しいようだ。本来の自然界からみたら本当に可笑しなことなのだけど、何もしないでいるということが何か手持ち無沙汰で不安に感じるらしい。
今までのものを全部手放せば一挙に救われるのだが、それが中々できないのもまた人情である。やっぱり「これまで作り上げてきた自分」を惜しむ気持ちがあるのかもしれない。まずは思い(を断ち)切って活元運動をやってみていただきたい。身を捨てたとき、一体どのように「浮かぶ」のか。ぜひ自己の身心をもって実証していただきたいところだ。


