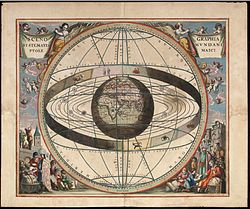「(整体になるには)どうすればいいのか」と問われれば、
それは深い呼吸(深呼吸ではなく)、重心の沈下、全身のゆるみ、言葉にすればだいたいこういった類になる。ところがそのどれもが整うための条件ではなくて整った結果訪れる精神身体現象である。
こちらは最初から余すところなく伝えているつもりでも、お互いの機が熟さなければ伝わらない。受け取り方がわるいのだと居直るのはもちろんよくない話で、「その時」を見極めて的確な刺戟で説くべきである。啐啄の機は何においても指導の急所である。
その一方で「整体」には完成もない。成ったと思っても次の瞬間はもうわからない。心の僅かな凝滞によってまた乱れる。ちょうど自転車が倒れないように絶えずハンドルを修正しつづけるようなものだ。言ってみればその無意識の平衡要求が一定に働いている状態を「整っている」と、こう呼んでいいのかもしれない。
面白いもので整えようとしている間は整わない。その「整えよう」をやめると秩序は現れる。出来ることなら人間が頭に描く「健康」など忘れて、今日一日精一杯生きることを勧めたい。「一日」の中にはそんな忘我の時節が何度も或るのだが、その時は気が付かないのだからそれを「妙」というべきか、面白いものだ。
とにかく一度でいいから徹底的に自我が落ち切る体験をするしかない訳で、「ああなるほど、これのことか」という、そういうもの。それは自分がやることで、人にどうこう言われるようなものではないのだ。
もとより整体をやるなら他人に一切要はない。自分自身が自分自身のためにやるだけだ。力があるなら「それ」を取れるはず。窮していればなお良し。悩みと成長は一つの現象の両側面である。それだけに「気づき」も早いはずだ。
但しインスタントを求める人にはインスタントが手に入る。何を求めるかはその人、生来の質によるところが大きいのも事実である。
命は雄大だ。その雄大さを人間の卑小な知識で狭めてはいけない。知識も智慧も、その他の一切合財も捨てた時に、必ず「残るもの」がある。それを見極めたら一先ずの「安心」は得られるだろう。更にそこから十年一日の心で鍛えていくことが肝要である。それを信じられる者だけ黙って門を叩けばいい。
しかし実際は千里の道など在りはしない。何時だって目前の一歩が全てなのだ。