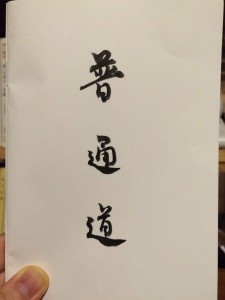この二か月ほど紹介などで「野口整体」を経由せずに個人指導を受けられる方が続いた。何が何だかわからないけど、とにかく「良くなる」と聞いて来られるのだが、整体の方法はすべて常識的な健康観や病気観とは真逆の視点で成り立っている。そのため「思想と価値観の共有」がない方には、うかつに技術など使えないなあと思ったし、力不足も感じた。西洋医療に例えて言えば、「手術」ということ一つとっても、多くの方に医療(治療)行為として認知されているからいいものの、少し見る角度を変えれば身体に傷を負わせる行為である。お互いに「これは治療だ」という共通認識がなければとても出来ない話だ。
そういう意味から言えば、整体というのは先ず生命の完全性を肯定した上で、如何にそれを阻害せずに(生命活動に則った刺戟で)最大限の成果を得るか、を考えている。ここでの刺戟というのは何も皮膚を介在するばかりでない。言葉でもいいし、表情でもいい。服装も、部屋の温度も、あらゆることが刺戟となってこれに呼応して身体(いのち)は動いていく。だから刺激が小さくて済むならそれに越したことはない。その変化の妙も個人個人まちまちであるし、またそのタイミングでもみな違う。頬をはたかれても表情一つ変えないような人が、さ湯を一杯出されただけで泣き出すこともあるのだから、人間心理の複雑雑性とは斯くの如しと言えよう。
一般医療の関係者とお話をしていると、やはり整体との決定的な違いは「個人の理解」ということに至ると思う。当然のことながら同じ人は二人といないし、また同じことは二度起こらない。「その人が何故そうなったのか?」ということに関して言えば、「そうなっている、その人」からしか学べないのだ。だから徹底その人を観ることが、治療の第一歩となるのは当然と言える。平たく言えば「観察」が第一義的問題であり、またそれが全てである。ここのプロセスに「価値」を見い出せない方には整体指導はむずかしいな思うこともよくある。
さて、身体に起った事というのはその時点では、「善い」も「悪い」もない反応(適応)である。「痒い」とか「痛い」とかいう事は生涯ついて周る話で、それをただ「悪い」という角度からしか見ないところが医療的視点の落とし穴である。それと同時に「良いと見る」ことも、また捉われであることを知らなければならない。そういう人間的見解を離れた上で、「どうしてそうなったのか?」ということを只ひたすら感じ、考えると、時に「妙だ」ということが見つかるのだ。そういう時には身体から「自然」や「美」というものが、大なり小なり減じている。
整体指導の方向性としては、生きた身体から「有機的な調和を害するもの」を徹底的に排除したい。大ざっぱに言えば、自然界で人間だけが有機的調和から逸脱している、といっても良いわけで、その自然性から離れるものが「理性」である。だからこそ、この理性の完全休止状態を「ポカン」と説き、この時の生じる動き(活元運動)にこそいのちの調和を取り戻す力が100%現れると言えるのだ。
しかるに、いろいろな治療方法方を探してきた人の中にはこのことが中々肯えない方がいる。「何かする」ということ数多くをやってきた人には、「何もしない」という選択肢にはガラクタ程度の価値も見い出せないのかもしれない。ポカンとすることは、身体の「自然」がフル稼働している状態で、そこに邪魔(理性)の入り込む余地がない。言うまでもなく、このとき身体は一番巧く動いているのである。
矛盾するようだが、常識的な健康観を脱することが容易ではないこともよく判っているつもりだ。逆にこれさえ成ってしまえば整体生活の95%は完成したとも言える話で、あとは実践あるのみとなる。生命を扱う世界も玉石混合なので、何が「真」であるかは自身で嗅ぎ分けていただくしかない。個人指導を受けるなら、まずは「そうかもしれないな」という程度でもよいので、野口整体と活元運動の理念に理解の姿勢が見えないとこちらも触れられないのだ。一方で説明責任も充分果たせていなかったことを反省した。そういう訳で自身の発信している言語をもう一度点検していこうと思っている。