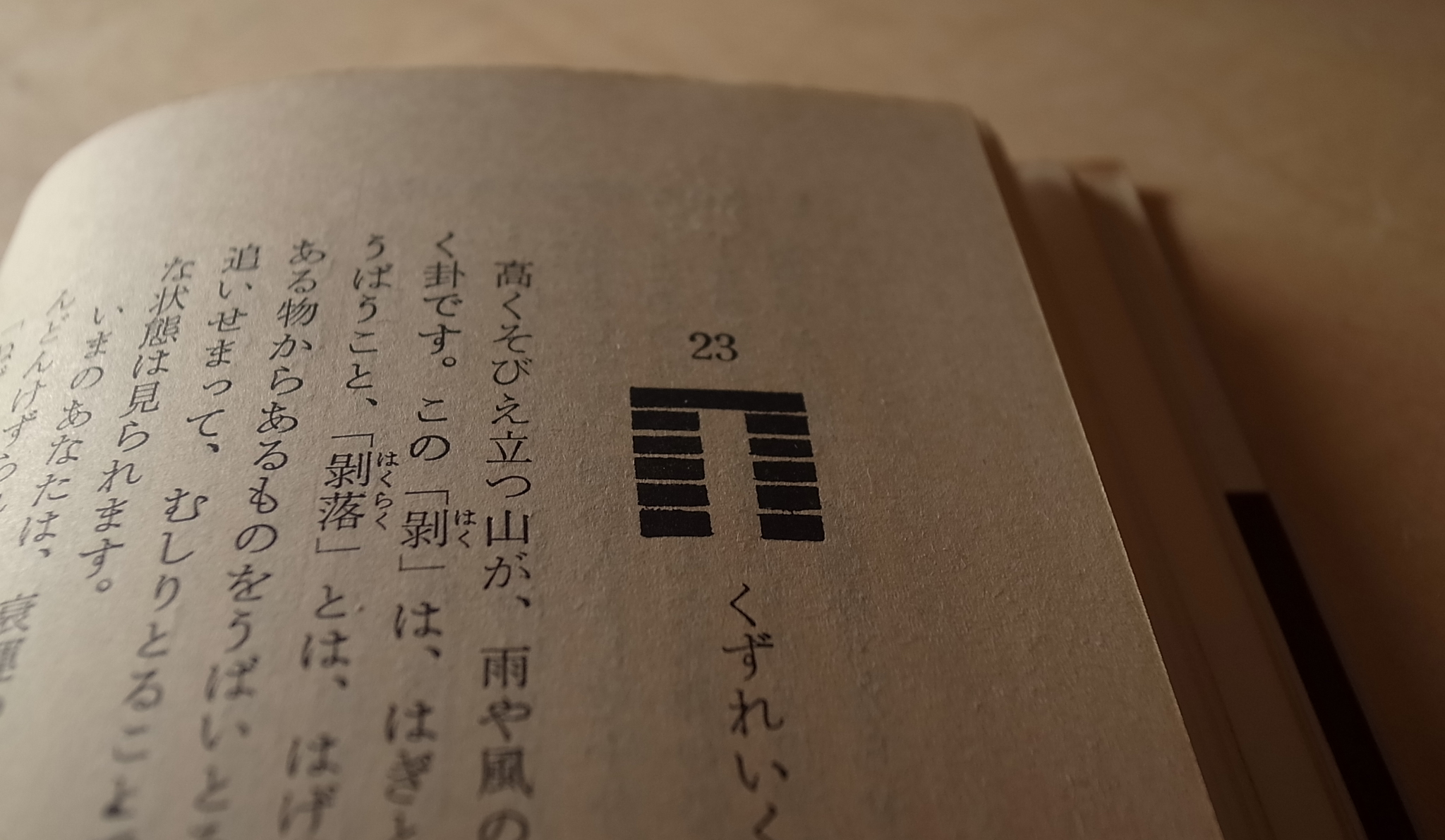初夏の陽気に伴い世相も若干だが落ち着いてきたような気がする。スーパーにはトイレットペーパーの姿が戻り、おもてを歩いても公園に行ってもマスクの着用率がわずかだが減ってきている。
そろそろ今回の騒動も終わりが近づいているのかもしれない。こうなってみると一緒になってわたわた騒いだ自分自身も恥ずかしく思えてくる。
そもそもが木の芽時は病気が出やすい。寒さでこわばっていた身体が動き出し、身の内外と再適応を図り始めるのが春という季節の特徴である。だからここまで暖かくなってしまえばもろもろ病気の発症率が下がるのは自明の理である。これから身心共に快活に動ける季節だ。
ところで整体法では肺炎は14日という。
つまり14日かけて病症を順々に経過することができれば、肺炎の必要のない身体にまできちっと整うということだ。これは演繹的な観念論ではなく、膨大かつ精緻な臨床経験によって得られた主観的事実として説かれている。
実のところ私自身が肺炎にかかった記憶もなければ、肺炎を発症している身体を観たことがないので、その点あまり語気をつよくして主張することはできないのだが‥。
ともかく先の整体法の論に拠って立つなら、その14日間を如何に心静かに過ごすかが鍵となる。そうすれば身心は本来の弾力を取り戻すと考えてよいと思う。
ただし自然経過とは野放図にしておくことではない。身体の要求に静かに耳を傾け、食するべくして食し、動くべくして動き、眠るべくして眠る、という無為自然の生活を心がけ、平素から訓練を積んでおく必要がある。錐体外路系の訓練法として活元運動の必要性もここにある。
もとより病気は苦しいものである。苦しいから病気としての意義もあり、治ろうとする働きもその苦しさと供にある。
そして今後そのような身体にはしまいとする心の態度も、その病気の苦しいことによって養われる。したがって主体的養生の生活も病苦によって支えられているのだ。
病気は衆生の良薬と釈迦は言ったそうだが、病症とは健康の中に包括される身心の自浄作用なのである。
ところが現代のように病症を健康と対立させ、これを駆逐しようと頭を熱くしているうちは病気の方もその宿主の頭を冷やすべくますます活性化するばかりだ。
西洋発祥の科学的医療は、その原点に於いて自他分離の二元対立を基礎として構築されている。分離はさらなる分離を繰り返し、ついには自分と身体を分離させ、身体の自己防衛の働きである病気と対立し、闘病などと言って自分の身体の正常な働きを相手に喧嘩をしているのである。
一般にはそれを「治療」と称しているのだが、つまるところ科学的な医療行為は病症・病巣と医薬との戦いという構図に落ち着く。その結果、治療自体が戦場となる身体を荒廃させる暴力になり下がっている。対立と闘争は必ず無限の連鎖を生む。この世のどこを探したって平和を創造するための聖戦なぞ存在しないのだ。
それにしても今回改めて目についたのは現代人および現代社会のエネルギーの余り様である。
マスクの取り合いで乱闘などまさに噴飯ものだが、それとは別にいま相当数の方が(正確な割合は把握していないけれども)在宅勤務という名の休暇を強いられている聞く。ところが、かれこれ一か月以上このような状態が続いているというのに往来で餓死者に出遭うこともない。
もちろん経済的に困窮している方も決して少なくないことを忘れてはならないが、一連の政策によって生じた個人の負債はそれなりに政府が受け持つ姿勢を示している。
全面的には依拠できないにしても、物質的豊かさを求めて邁進してきた社会も知らぬ間に大変な余剰を抱えるようになったものである。
余剰は鬱滞を生み、鬱滞は速やかに鬱散を要求する。
鬱散行為のもっとも単純化した形態は破壊である。
例えば、胸の内に不平を忍ばせている人は知らずに物を壊す。物を壊さなければ他人を攻撃し、そのような行為に抵抗感のつよい人は一番身近な自分を壊す。
自分で自分の顔を壊す「ふくれっツラ」などは自己破壊のなかでもっとも可愛いものだろう。
そこから発展して意識的になされる自傷行為などはまだわかりやすいが、無意識に行われる病気や怪我の大半はこうした自壊現象として行われるものが存外多いのである。
そうした生体エネルギーの鬱散が集団で行われた場合、その端的は戦争である。しかし大国間の直接的な大戦がなくなった今、エネルギーの噴出口が閉ざされた結果、ネチネチとしたいがみ合いや不信の増大へと変態している。それでも隣国に毒ガスを撒いたり爆弾を落とすよりははるかにマシだが、やはり人間の自然の美しさが現れているとはいえまい。
俗にいう先進国(もはや何が先進なのかわからないが)の文明生活とは、全般に餓死者、病死者を出さないように、怪我人を減らすように、すなわち「死」をできるだけ遠ざけるべく発展してきたと考えられる。それに付随して労働時間の短縮と生産性の向上を図り、なるだけ時間と体力を余らせるべく成長してきたとも言えるだろう。
労働から解放された時間と体力で「自由にやりたいことをやる」という心算だったのかもしれないが、蓋を開けてみればその余った体力で病気を増やし、さらに治療法を巡って身心を疲弊させ、国家の財源を蝕んでいる。それでなくても元々人間は先の理由から、他の動物よりも余分にイライラしたりクヨクヨしながら生活する方向へと文明を成長させてきた。
私見としては、今回の感染症に因んだ一連の騒動もそうした余剰体力と金余りに対する生理的な鬱散要求だと思っている。言ってみれば、近代以前まで盛んに催された土俗的な「祭り」のようなものである。
古来より祭りとは人間に内在する野性的衝動を、時間と場を区切りるなど一定のルールを敷いた上で効率的に噴出させ、事後に生理的な平衡に向かわせる文化的行為である。そのようなある種の健全さに向かう貴重な行為も、近年は人間が「利口」になったせいか概ね縮小傾向にある。
そうして行き場を失ったエネルギーは様々な排出口を見つけては、千変万化して昇華噴出を繰り返しているのが現代社会の特徴の一つと言える。
いわゆる先進国の文化に浸った人ほど、神様や悪魔、仏様や鬼といった前近代的な漠然とした概念では、強い情動を引き起こし噴出に向かわせることは難しい。
そこはやはり「カガク的」という、現在もっとも強力に信仰を集めている理念に沿う形式である程に、その扇動効果は絶大となる。このカガク的と言うのはなかなか曲者で、科学を真に理解する専門家に言わせれば極めて論理性の低い観念主義なのだが、この際そのようなことはどうでもいいのである。
いわばゾウでもクジラでも通れるようなザルの理屈でも、民をしてその鬱屈した野生の噴出を可能とするだけの「それらしい理由」さえ確立すればいい。これによって集団心理というものはいともたやすく生理的噴出エネルギーの発露に向かって驀進していくのである。
科学と言うのは本来の性質からいえば上質な理性をその思想展開の基盤とし、尚且つ動物的な感情や生理的な欲求を下位に置いた上で、極めて冷静に自然生命に秩序をもたらし人間社会にとって有効活用に導くものだと思っていた。
しかしその科学を扱う人間もやはり感情と情動をその思考活動の基底に置き、エネルギーの集中と分散の波に支配される自然の生命体であることには変わりはなかったのである。今回の感染症騒動はそれを雄弁に語っているように思われる。
改めて先の主張に立ち返るが、かような人間の生理構造に照らすことで本件を現代式のお祭りと直感した次第である。特に江戸末期、日本各地においてほぼ無目的的、同時多発的に起こったといわれる「ええじゃないか」を彷彿とさせる。それが情報伝達技術の進化と相まって、勢いワールドワイドになるのは已むをえまい。
余剰エネルギーの分散が済めば自ずと勢いは収束し、やがて分散のエネルギーは流転して集中の波へと回帰する。だから体力の余った人はこの機に乗じて騒げるだけ騒いだらよかろうし、もとから集中分散の平衡がとれている人は静かな自分の世界から悠々と事の成り行きを眺めることだろう。
話はそれるが教育も医療もそうした根源的な生理的エネルギーの存在を無視し続ける限り、人間を自在に導く術を実現することは難しい。それは個人においても公においても、である。
フィットネスジムの増加も人間の自然の心が生んだものにはちがいないが、もっと身近なところで自分の要求したことをさらりとやってのける人間を育てていく、そういう方法はないだろうかと思いを巡らせる。
整体法はその一翼を担う立場にあるけれども、その完成された理論とはうらはらに実践も普及も全く追い付いていないのが現状である。
原因はさまざまに考えられるが、もともとが創始者である野口晴哉という傑出した人物によって構築されたものだけに、属人化のつよい一代限りの名人芸になりつつある感は否めない。
それに加え「自分の健康は自分で保つ」「自然の生命へ還れ」といった理念もきわめて単純明快だが、それだけに安易な誤解へと流れやすいようである。まあそれは他のメソッドや宗教的な教義でも同じことは言えるかもしれない。親鸞の念仏とて同様、その死後はすぐさま法が乱れた。
理解というのは個人の知性に委ねられるもので、教える側にばかり責任を負わせるには無理がある。いわば教化とは他力と自力の相乗効果といえそうだが、それでも提供する側は自分の役割を果たすべく、最大の努力を惜しんではならない。
何であれ人間の生理的な構造と言うのは人類発生から現在に至るまで、そして今後何万年経ってもおそらく変わらない。
仏の掌上で飛び廻った孫悟空と同様に、いかなる生命も自然の法則からは逃れられないのである。その大自然の一部である人間の非や欠陥を一々あげつらうより、もう一つその構造を冷静な眼で観察し理解を深め、情熱をもって使いこなす道を開拓していく方がずっと生産的である。
そういう意味で課題は山積みなのである。当面は病気に対する捉え方の見直しが早期に図られることを願ってやまない。それに加えて心は心、体は体、という風にほうぼう別々に研究が進む中で、この二つを統合しつつ生きた人間を包括的に理解していく学問の必要性をつよく感じる次第である。
実のところ既存の科学の欠点を補完すべく、既にニューサイエンスという潮流が生まれてから久しい。医療の領域でも心身医学の発生など、既存の科学的見識を超えた形で行われる、生きた人間を生身の目で探求する動きが活発である(真に科学的とはこのような態度であると信じる)。
一方で整体法は主観主義に基づいた経験的な総合人間学と言える。それだけに科学的な客観性や再現性を求めることに困難を余儀なくされ、なおかつ一定の質を保持しつつ普及・存続させるにも様々な障害がある。
今後は可能な限り客観性を保持しながら、そのメカニズムと教義の普遍性を論証していくことが整体法を実践する者の使命だと考える。何より自分自身が整体法の質的低下に加担しないよう、客観性と同等に主観の練磨を怠らぬことが何よりも大事だろう。偏りのない純粋な主観をもって、事実を公正に見つめることが真理に至る唯一の道だ。
野口晴哉は整体法の源泉となる心を説くために近代医術の祖であるヒポクラテスの理論を引いている。その一つは、「事実以外に権威はない」という一節に要約される。整体法とはいかなるものか、その答えはやはり事実の集積と体現による実証に勝るものはないようである。